キャンプの醍醐味のひとつの焚き火。
ゆったりと焚き火のゆらめく炎を眺めているととても癒やされます。
私は焚き火が大好きなので、キャンプでは毎回必ず焚き火をします。
ただ、焚き火は必要知識が無いとなかなか火が点かなかったり、最悪ボヤ騒ぎになってしまうかもしれません。
本記事では、失敗しない焚き火のやり方と必須の道具を解説します。
・焚き火の手順が分かる
・焚き火に必要な道具が分かる
・安全な焚き火ができる
焚き火の必須道具と便利な道具
焚き火をするのに必ず準備するべき道具になります。
- 焚き火台
- 焚き火シート
- 薪
- 火ばさみ
- チャッカマン、ライター
- 耐熱グローブ、軍手
必須ではありませんが、準備すると便利な道具です。
- 着火剤
- サバイバルナイフ、手斧
- のこぎり
- 火消し壺、火消し袋
- 火吹き棒
- 風防板
それぞれの道具について解説していきます。
焚き火台
近年、ほとんどのキャンプ場では地面に薪を直接置いて直火の焚き火を禁止していますので焚き火台は必須。
禁止の理由としては、直火で焚き火をすることにより、地面の自然にダメージがあったり、火災などの危険性があるからというものがあるからです。
焚き火台には様々な種類がありますので、人数やスタイルに合わせて選びましょう。
おすすめの焚き火台
焚き火シート
焚き火台シートは焚き火台の下に敷く不燃素材のシートで、周囲の燃え移りを防いだり、焚き火台の熱から地面の自然を守るために敷くものになります。
焚き火台からこぼれた灰を集めて片付けしやすくなったりしますので、後片付けにも役立ちます。
おすすめの焚き火シート
薪
焚き火に使う薪は、大きく分けて「針葉樹」と「広葉樹」の2種類があります。
針葉樹は、スギやマツ、ヒノキなど、葉が針のように細く尖った木です。
- 火つきがよい
- 燃焼時間が短い
- 煙が多い
- 比較的やわらかい
針葉樹は、火つきがよいため、最初の火つけに適しています。
ただし、煙が多いため、風の強い場所では注意が必要。
広葉樹は、カシやクヌギ、ナラなど、葉が手のひらのように広がった木です。
- 火つきが悪い
- 燃焼時間が長い
- 煙が少ない
- かたいものが多い
広葉樹は、火つきが悪いため、最初の火つけが難しいです。
しかし、燃焼時間が長く煙が少ないため、焚き火を長時間楽しみたい場合に適しています。
おすすめとしては、両方の種類の薪を用意して、最初は針葉樹で火をつけて、安定してから広葉樹を使用すると長く焚き火を楽しめます。
火ばさみ
火ばさみは、薪を追加で入れたり、燃えている薪を動かしたりするのに必要です。
耐熱性と耐久性に優れたものを選びましょう。
先端が細くてギザギザしているものを選ぶと、薪を扱いやすくなります。
チャッカマン、ライター
チャッカマンやライターは火つけをする必需品です。
使い捨てタイプや充填式のものがあります。
火口が長くなっている物だと着火しやすく、風が強いときでも着火できる強力なチャッカマンやライターがあると便利です。
最初は100円ショップの物で十分ですが、専用品は高機能で火がつけやすくおすすめ。
耐熱グローブ、軍手
耐熱グローブや軍手は、焚き火やバーベキューなどの火を使うアウトドアアクティビティに欠かせないアイテムです。
火傷から手を守るためには、耐熱性やフィット感など、適切なものを選ぶことが大切です。
耐熱グローブの種類。
- 革製の耐熱グローブ
革製の耐熱グローブは、耐熱性が高く、長時間の着用でも快適です。
また、防水性にも優れているため、水仕事にも適しています。
- アラミド繊維製の耐熱グローブ
アラミド繊維製の耐熱グローブは、軽量で耐熱性が高く、伸縮性にも優れています。
着火剤
着火剤は無いとダメではありませんが、使用すると火をつけやすく、なかなか薪に着火しないという失敗をしなくなります。
選び方のポイントは火をつけやすく、火持ちがよいものを選ぶことが重要です。
着火剤には大きく分けて、以下の2種類があります。
- 固形タイプ
固形タイプは、木屑などに油脂やパラフィンワックスを浸透させて固めたものです。
火をつけやすく、火持ちもよいため、初心者にもおすすめです。
- ジェルタイプ
ジェルタイプは、アルコールを主成分とした燃料を、水やグリセリンなどで固めたものです。
火をつけやすく、煙が少なく、火持ちも良いため、焚き火を長時間楽しみたい場合におすすめです。
サバイバルナイフ、手斧
焚き火をする際には、薪を切ったり割ったりするために、サバイバルナイフや手斧があると便利です。
薪を切ったり、枝を割ったりすることが多い方は、サバイバルナイフがおすすめで、薪を割るのに特化したい方は、手斧がおすすめです。
サバイバルナイフは、刃渡りが10cm以上のナイフです。
薪を切ったり、枝を割ったり、野菜を切ったりなど、幅広い用途で使用できます。
サバイバルナイフを選ぶ際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 刃の長さ
刃の長さは、用途によって選びましょう。薪を切ったりするには、刃渡りが15cm以上のものがおすすめです。
- ブレードの形状
ブレードの形状は、刃先が鋭く、刃厚があるものがおすすめです。刃先が鋭ければ、薪を切ったり、枝を割ったりするのに便利です。刃厚があるほど、耐久性が高くなります。
ナイフを叩いて薪を割るバトニングをするならば、フルタングのものが必須。
- ハンドルの形状
ハンドルの形状は、握りやすいものがおすすめです。また、滑りにくい素材のものを選ぶと、安全に使用できます。
手斧
手斧は、斧の一種で、片手で扱えるサイズの斧です。薪を割るのに適しています。
手斧を選ぶ際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 刃の長さ
刃の長さは、薪の太さに合わせて選びましょう。薪が太いほど、刃の長い手斧がおすすめです。
- ハンドルの長さ
ハンドルの長さは、使いやすい長さを選びましょう。ハンドルが短いと、力が入らず、薪が割りにくくなります。
- 重量
重量は、使いやすい重さを選びましょう。手斧は、片手で扱うので、重すぎると疲れてしまいます。
のこぎり
焚き火ののこぎりの選び方
焚き火をする際に、薪を切ったり、焚き付けを細くしたりするためには、のこぎりが必要です。焚き火ののこぎりを選ぶ際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 刃渡り
刃渡りは、薪の太さや、切断する頻度によって選びます。刃渡りが長いほど、太い薪も切断しやすくなりますが、持ち運びにくくなります。初心者や、小枝や細い薪を切断することが多い場合は、刃渡り17cm~24cm程度のものを選ぶとよいでしょう。
- 刃の形状
刃の形状は、切断する薪の種類によって選びます。小枝や細い薪を切断する際には、切れ味が良く、軽量な「薄刃」がおすすめです。太い薪を切断する際には、切れ味と耐久性に優れた「厚刃」がおすすめです。
- 素材
素材は、耐久性や切れ味によって選びます。ステンレスは、耐久性と切れ味が良く、錆びにくいのが特徴です。アルミは、軽量で持ち運びやすいのが特徴です。
- 機能
機能は、使いやすさや利便性によって選びます。折りたたみ式のものは、持ち運びやすく、収納場所に困りません。替刃式のものは、刃こぼれや切れ味が悪くなったときに、刃を交換することができます。
焚き火ののこぎりを選ぶ際には、上記のポイントを押さえて、自分に合ったものを選びましょう。
火消し壺、火消し袋
焚き火を安全に楽しむためには、火消し壺や火消し袋を使って、火を完全に消すことが大切です。
火消し壺や火消し袋を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。
- 容量
火消し壺や火消し袋の容量は、焚き火の規模に合わせて選びましょう。小さすぎると、炭や灰を完全に消すことができない可能性があります。
- 素材
火消し壺や火消し袋の素材は、耐熱性と耐久性のあるものを選びましょう。また、熱伝導率の低い素材を選ぶと、持ち手が熱くなりにくいというメリットもあります。
- 使い勝手
火消し壺や火消し袋は、使い勝手も重要です。持ち運びやすいサイズや、蓋の開け閉めがしやすいものを選びましょう。
火消し壺
火消し壺は、焚き火の灰や炭を完全に消すのに適した道具です。
- 金属製
金属製の火消し壺は、耐熱性と耐久性に優れています。また、熱伝導率が高いため、火を早く消すことができます。
- 陶器製
陶器製の火消し壺は、和風の雰囲気を演出するのに適しています。また、熱伝導率が低いため、持ち手が熱くなりにくいというメリットもあります。
火消し袋
火消し袋は、軽量でコンパクトに収納できるのがメリットです。
- 耐熱性・耐久性
火消し袋は、耐熱性と耐久性のある素材を選びましょう。また、熱伝導率の低い素材を選ぶと、持ち手が熱くなりにくいというメリットもあります。
- サイズ
火消し袋は、焚き火の規模に合わせてサイズを選びましょう。小さすぎると、炭や灰を完全に消すことができない可能性があります。
焚き火の火消し壺や火消し袋は、安全に焚き火を楽しむために欠かせない道具です。上記の点を参考に、自分に合った道具を選んでください。
火吹き棒
焚き火を長く楽しむためには、火吹き棒があると便利です。火吹き棒は、火に息を吹き込んで火力を上げる道具です。
火吹き棒を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- サイズ
火吹き棒のサイズは、自分の身長や手が届く範囲に合わせて選びましょう。
- 素材
火吹き棒の素材は、ステンレスやアルミなどの耐久性のあるものがおすすめです。
- 形状
火吹き棒の形状は、先端が細いものを選ぶと、火力をピンポイントで上げることができます。
- 価格
火吹き棒の価格は、安いものから高いものまでさまざまです。自分の予算に合わせて選びましょう。
火吹き棒のおすすめ
ここでは、おすすめの火吹き棒をいくつかご紹介します。
- ステンレス製の火吹き棒
ステンレス製の火吹き棒は、耐久性があり、長く使うことができます。また、錆びにくいので、キャンプや登山などのアウトドアで使うのに適しています。
- アルミ製の火吹き棒
アルミ製の火吹き棒は、軽量で持ち運びに便利です。また、熱伝導率が高いので、火を早く大きくすることができます。
- 伸縮式の火吹き棒
伸縮式の火吹き棒は、収納サイズが小さいので、持ち運びに便利です。また、長さを調節できるので、さまざまな場所で使うことができます。
火吹き棒の使い方
火吹き棒を使う際は、以下の手順で行います。
- 火吹き棒を火の上に持っていき、息を吹き込みます。
- 火の中心部に息を吹き込むようにすると、火力が上がります。
- 火が勢いよく燃え上がってきたら、火吹き棒を離します。
火吹き棒は、焚き火を長く楽しむための便利な道具です。ぜひ、自分に合った火吹き棒を見つけて、焚き火を楽しんでください。
風防板
焚き火をする際に、風の影響を受けにくいように風防板を設置すると、より安全に楽しむことができます。風防板には、さまざまな種類があるので、自分の用途や好みに合わせて選ぶことが大切です。
風防板の種類
風防板には、大きく分けて「金属製」「布製」「折りたたみ式」の3種類があります。
金属製
金属製の風防板は、耐久性と強度に優れています。また、反射率が高いため、焚き火の明るさをアップさせることができます。ただし、重量があるため、持ち運びには不向きです。
布製
布製の風防板は、軽量で持ち運びに便利です。また、折りたたみ式のものが多く、収納スペースをとりません。ただし、耐久性や強度が金属製に比べて劣ります。
折りたたみ式
折りたたみ式の風防板は、収納スペースをとらず、持ち運びに便利です。また、金属製や布製の風防板と比べて、価格が安い傾向があります。ただし、耐久性や強度が金属製や布製に比べて劣る場合があります。
風防板のサイズ
風防板のサイズは、焚き火台のサイズに合わせて選ぶことが大切です。焚き火台よりも風防板が大きすぎると、風が通り抜けて、風防板の効果が薄くなります。逆に、焚き火台よりも風防板が小さすぎると、風が焚き火台に直接当たってしまい、火の粉が飛び散る恐れがあります。
風防板の素材
風防板の素材は、耐久性や強度、反射率などを考慮して選ぶことが大切です。
耐久性と強度
風防板は、風や熱に耐えられる耐久性と強度が必要です。特に、風の強い場所で焚き火をする場合は、耐久性と強度に優れた風防板を選ぶようにしましょう。
反射率
風防板は、反射率が高いと、焚き火の明るさをアップさせることができます。
風防板の機能
風防板には、さまざまな機能が付いたものがあります。
- 五徳付き
- スタンド付き
- 収納袋付き
五徳付きの風防板は、調理をする際に便利です。スタンド付きの風防板は、焚き火台を安定させることができます。収納袋付きの風防板は、持ち運びや収納に便利です。
焚き火の風防板は、焚き火を安全に楽しむために欠かせないアイテムです。自分の用途や好みに合わせて、最適な風防板を選びましょう。
まとめ
焚き火は、単に暖を取ったり料理をしたりするための道具ではありません。その炎や音、香りを楽しむことができます。
焚き火を囲んで、家族や友人と語り合ったり、音楽を聴いたりするのもおすすめです。
焚き火は、自然の中で過ごすアウトドアの醍醐味を味わうことができる、特別な体験です。ぜひ、安全に楽しく焚き火を体験してみてください。

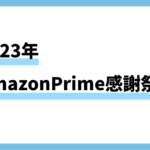

コメント